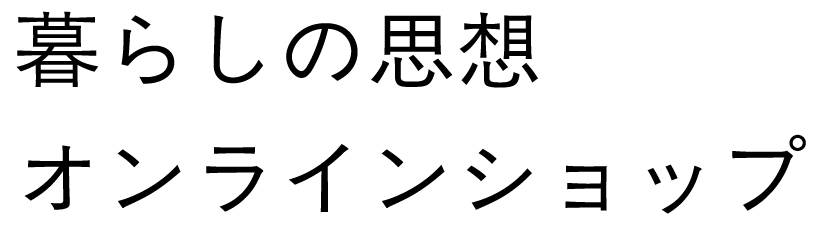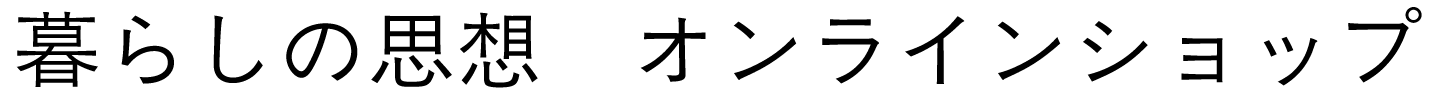『季節風』『生活』 島尾伸三

はじまり
しんととしんとと
一両編成の路面電車に揺られ、のんびりと向かいます。都電荒川線の小台駅に到着すると、アップルロードとの交差点、車道の真ん中に降ろされて、文具屋とパチンコ屋を両手に、旧小台通りへと進みます。商店街と住宅地の合いの子のようなこの通りは、小台銀座 商店街。シャッターの降りたお店の間にも、電気の灯る小さなお店がちらほらと、かつての賑わいのカケラがまだ少しだけ残ります。
そこは、成熟した下町の商店街です。かつては、自転車も通れないほどの賑わいだった と、20年以上この通りを知る人は、みな口を揃えて教えてくれます。いくつもの商店が立 ち並び、八百屋の威勢のいい掛け声がこだまして、活気のあった通りも、時代の流れに逆 らうことなく、今では静かにひっそりと、そこにあり続けます。
その商店街の通りの中ごろには、三代続く銭湯「梅の湯」があります。ここの前だけは自 転車がずらっと並び、この街の銭湯文化を確かに引き継いでいます。小道を挟んでもう一 軒先には、二代続く中華屋「だるま軒」があります。このお店の存在なくして、私たちは 成り得ないほどにお世話になっているのですが、話し始めたら長くなってしまいますから、それはまた今度。商店街としては盤石な並びに挟まれて、私たちはお店「暮らしの思想」を構えます。
お店、のようなもの
お店といっても、お店のようなものかもしれません。もちろんお店では、本や、花、パンやお菓子を売ります。それぞれの専門性を持ち合わせて、他にはないユニークなお店、そして空間だと自負しています。それでも「のようなもの」と表現するのは、まだまだお店 になりきれていないような心細さと、それは一つの手段として、より広がりを持ったもの として「暮らしの思想」を捉えていきたいという思いからです。
お店がオープンしてから半年が過ぎ、不安と野望が心の中を渦巻きながら、どうにか歩んでいる、そのような心持ちからかもしれません。まだまだ何かになりきらない、何かに断 定もせず、曖昧さ加減も受け入れながら、「のようなもの」として。
本連載は、「暮らしの思想」を主宰するナカムラソラが「暮らしの思想、のようなもの」 と題して、毎回数冊の本を紹介しながら、お店と暮らしを行き来しながら、考えたことを綴るものです。
それでは。 しんととしんとと。
どうにかこうにか、半年
お店をやることがこれほど大変なことだとは、店名を考えていた頃の私には、露も思いませんでした。
東京の左半分で育った私が、こちらの地
域に越してきたのは大学四年生の頃です。渋谷の 本屋でバイトしていた私は、小売としての本との向き合い方に限界を迎え、その頃ちょう ど旅先で出会ったブックディレクターという職に惹かれ、今も務める会社の門を叩きました。ブックディレクションというのは、大きくいうと本のある空間をつくる仕事です。公共図書館から、本屋、ホテルや病院、街中の小さな本棚まで、数十万冊からたった一冊ま で、大小さまざまなライブラリーの中身をつくる仕事です。
その傍らで、華道家の増渕若雨さんと始めたのが「暮らしの思想」というお店です。本屋 と花屋、そこにカフェも合わせて、三者三様の専門性
を持ち合わせ、一つの空間をつくり ました。普段はクライアントワークとして、外からお店や空間づくりに携わっているものの、ここでは自分がオーナーです。平日は会社員として働きながら、休みの日や仕事の合間を縫って、どうにかこうにか今のお店を続けております。
おままごとのような店主
お店を開業してから半年。もちろん当初描いていたようには上手くはいきません。お店を 「つくること」と「続けていくこと」には、やはり大きな隔たりがありました。それは、 依頼を受けて行うこれまでの仕事とは、まったく異なるものだと身をもって実感したのです。
「暮らしの思想」という言葉の響きに惹かれて、店名はこれしかないと思った私には、暮らしにおける悲壮が欠落していたのかもしれません。どこか他人事のような感覚です。 「なるようになるさ」なんて言いながら。
そんなやけっぱちな楽観主義者でなければ、こんな時代に本屋を始めようだなんて思わないのかもしれませんが。
もちろんこの時代に、この商店街で本屋をすることに、大義名分をいただいていないわけ ではありません。お店を始める理由を聞かれたら、紙の本の未来や、商店街との関係を話 します。それでも、それは自分がお店を続けていくための根本的な動機にはならないのだ と思います。そこには「承認される過程」が必要でした。つまり、自分たちが掲げた目標・目的に対して、なんらかのフィードバックを根源的に必要としていたということです。それは、売上や来客数、それぞれのお客さんからの反応、認知度……さまざまな側面があ りえますが、お店である以上、「どれくらい商品が売れたのか」というところは、最終的 に結果として私たちの前に現実を突きつけます。その日の売り上げに、一喜一憂してしま うのです。
クライアントワークである場合には、本やお花が求められるとき、基本的にそれらの効果 は定量的に測れるものではありませんから、社会一般で共有できる感覚に訴えかけること で、その価値に納得してもらうことがすべてでした。けれど、お店を経営するとなると、自分自身がその価値に納得しなければなりません。だって、自分がクライアントですか ら。どれもこれも自作自演です。ですから、得られた結果に対しては、「まあ、そういうものだよ」と言い聞かせるしかないのかな、というのが現時点での考えです。まあ、どうにかなるよと。
あまり大袈裟にものを考えすぎてはいけない。ありふれて、ありきたりかもしれないけれ ど、それは確かに唯一無二で、絶対的なもの。それ自体で、愛されるべきもの。
それが私たちの「暮らしの思想」の考え方です。思想といっても、地に足の着いた、誰もが持ちうるものとしているものの、それを主宰する本人は、どこか浮き足立っているよう です。側から見れば、それはおままごとのような、滑稽で、少し華やかで、そしてどこか 切ない感じさえも漂います。本人はいたって本気なところが、余計にそう見えてしまうの かもしれません。
こうしておかしく戯画的に表現してしまうのは、振り返りながら文章を書いているから で、出来事を、ここにある身体からペリペリと剥がしているから。リアリティの所在なん てものは、どこかに置いてきてしまったような気がしています。その態度は、無責任なものかもしれませんが、ふっとその身に起こる出来事から切り離し て、あたりをもう一度見渡し、見えていなかったけれどすでにそこにあるものに気づく。 そのような瞬間に、私は希望のようなものを抱いているのかもしれません。そんなまなざ しに、ずっと憧れを持っているからでしょうか。
推しファミリー
私には、「推しファミリー」なるものがあります。シルバニアでも、アダムスでもありま せん。島尾伸三、潮田登久子、しまおまほ(左から順に父、母、娘)の3人の家族です。 それぞれ写真や漫画、エッセイなど、さまざまな媒体で表現活動をされていますが、彼ら のつくる本は、なぜだか必ず私を魅了します。いずれの作品にも「家族」がうつりこみます。三者三様、それぞれの視点を通して、私たちは彼らを覗き見ることができるのです。一つの家族であっても、それぞれパラレルな風景がそこにはあって、私たちは勝手に重層的な物語をそこに描くことができる。そして、 父と母にはそれぞれの家族があり、また娘にも新たな家族が生まれます。こうして物語は、どこまでも広がっていくのです。
島尾さんのまなざしに、私はどこか惚れ込んでいるようです。彼の写真や文章には、劇的でも、大袈裟でもない、どこまでも平等に世界も自身も捉えているような感覚が流れてい ます。低調なビートが、ずっと鳴り続けているようです。感情の昂りは見えないけれど、 何でもないような日常への愛おしみを、感じずにはいられません。


風のなかに包まれながら
『季節風』『生活』いずれもみすず書房から出版されたその本は、とても不思議な本です。 本の体裁としては、島尾さんによる短いエッセイと写真で構成された、ささやかな一冊です。声高に何かを主張するわけでもなく、ページをめくるたびに思わず肩の力が抜けてしまうような短さで、ささやかな出来事が淡々と記されていきます。季節の隙間に落ちる影のかたちや、散歩の途中で出会った誰かの表情。どれも説明されきらないまま曖昧に、ただそこに置かれていくだけなのに、不思議とこちらの身体のほうが、それを受け止めてしまうのです。
『生活』には、著者であるキュウリと、妻の西洋ナシと、子どもの白磁のニンフとの日常生活が描かれています。あくまでこれはキュウリから見た日常であり、世界であるのだということがここで示されます。自分をキュウリと、妻を西洋ナシと比較させるところに、作家の自意識と自己卑下を抱えながらも、どこかいやらしさとは無縁な、純粋ゆえの不器用さが通底しています。
写真もまた、文章とおなじく飾り気がありません。撮ろうとしたというより、「そこにあるものが写ってしまった」ような佇まいがあって、湿度を含んだ生活の匂いがふっと漂っ てきます。どこか遠い異国の情景のようでいて、読み終えたあとには自分の部屋の片隅のようにも思える。そんな距離感の曖昧さが、この本の魅力だと感じています。
コンポラ写真としての初期の仕事にも、その距離感はほとんど変わらないように思います。都市の路地や人々の日常を、ドラマに仕立て上げることなく、そのままの温度で受け 止めるスナップ。説明的でも決定的瞬間でもないのに、フレームの隅に置かれたものたち が、ふと主役に入れ替わってしまうような写真です。個人的なまなざしが、社会の風景を そっとすくい上げる。そんなコンポラ写真の気配が、彼の写真には静かに流れていて、その「平熱のまなざし」は、あとから書かれていく文章ともどこかで呼応しているように感じます。
また特徴的なのは、写真には必ずキャプションが入ることです。妻と子どもがお昼寝している写真には、
「昼寝/何事もないのに、何かがゆるみ、/A nap / is completely uneventful, yet something loosens」
子どもがこちらを見ている写真には、
「妻が出かけた日/そして、しぼみ、/A day my wife was out / and shrinks」
といったように、写真の情景がより浮かび上がってきて、その断片的な瞬間に奥行きを与えてくれます。
島尾さんのこのまなざしは、世界を均等に照らします。何かを特別扱いしないし、逆に切り捨てもしない。淡々とした記録のようでいて、手触りだけが妙に残る。その感覚が、私はずっと忘れられません。私はそこに、愛すべきものを感じずにはいられないのです。
暮らしは思想のふりをして
お店を始めて半年。毎日やってくる小さな出来事の積み重ねに、私は思わぬかたちで鍛えられています。花の水を替え、パンをこね、棚の中で本を綺麗に整える瞬間。どれも一見すると「仕事の作業」のようですが、ふとした拍子に、それが自分の考え方そのものを形 づくっていることに気づきます。しゃがみ込んで子どもたちと触れ合って、たわいのない天気の話をして、たまに本を紹介したりして、お客さんと日々会話します。
暮らしは、いつも思想より先にやってくる。 そして、気づけばこちらが「思想のようなもの」を後から追いかけている。『季節風』『生活』を読むと、そのことを思い出します。ページをめくるたび、生活の中 の微細な揺らぎが、そのまま「考える」という行為へとつながっていく。その距離の短さが、どうしようもなく愛おしい。
「のようなもの」という居場所
この連載のタイトルを「暮らしの思想、のようなもの」としたのは、どこか島尾家の物語に触れたときの感覚に近いものが、自分の中にもあるからです。
はっきりした思想でもなく、洗練された暮らし術でもなく、ただそこに流れている時間の 呼吸を、そっとすくいとるような態度。その曖昧な領域に、私はお店を開いたときから ずっと救われてきたのだと思います。
お店は「まだお店になりきれていない」し、私も「店主になりきれていない」。でも、その未完成のまま漂っている、宙吊りな状態こそが、案外いまの時代を生きるための知性なのかもしれません。島尾さんの本は、そんな気づきを静かに押し広げてくれます。大きな 声ではなく、気配で語るように。読んだあとに、ひとつ深呼吸したくなるように。
『季節風』『生活』を読むと、部屋の空気が少し変わります。静けさの粒子が舞い、光が やわらかく折れ、目の前の風景がすこしだけ輪郭を取り戻す。本は、生活の中にそっと置かれただけで、思想の入口になります。花瓶の水を替えるようなごく普通の行為が、考える時間にもなる。
この連載では、そうした「思想としての暮らし」を、そして「暮らしとしての思想」を、 本を介しながら探していきたいと思っています。未完成でもよくて、断片でもよくて、読んだ本のこと、その日のお店のこと、暮らしの隙 間でふっと立ち上がった思考のかけらを、これから少しずつ綴っていけたらと願っています。